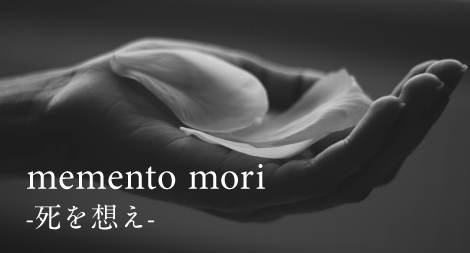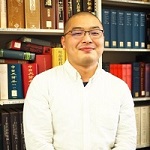(2017/7/21追記)
本講座(第1回)は2017年3月22日をもって受付を終了しました。
現在、第2回(2017年10月3日開講)の受講登録を受け付けております。
こちらのページをご参照ください。
講座内容
memento moriというラテン語は「死を想え」という意味で、現在は幸せに生きている自分自身もいずれは死を迎えることを忘れるな!という警句です。特に中世末期のヨーロッパ、ペストが蔓延するなどして逃れようのない終末観の中で享楽的な生活におぼれるキリスト教徒に対して発せられたこの言葉は、現世での楽しみや贅沢が虚しいものであることを強調するものであり、来世に思いを馳せるきっかけとなりました。
”Man is mortal.(人は死すべき存在である)” と言われるように、われわれ人間はいつか必ず死を迎えます。しかし死んだらどうなるのかと言った、古い時代からの永遠の疑問は、未だ解き明かされないままです。死後世界へと旅立った人々の誰一人として、この世に戻ってきた人がいないからなのでしょう。
そのため正解のわからない死をめぐって、人はさまざまな生活様式(=文化)を創造してきました。授業では現代日本人の死の文化を中心に、「死」について考えます。
なお、本講座は、「東北大学で学ぶ高度教養シリーズ」の第一弾となります。
第1週:死とは何か?
- 死-問題の所在-
- 死を考える視座
- 現代日本の死の状況
- 死の語義
- 霊肉二分論
- 死の起源の神話
- 死と宗教
- 死をめぐる民俗
- 死の認定
第2週:死者と生者の接点
- 死者とは誰か
- 葬送儀礼の構造
- 盆行事にみる死者と生者
- 死者との出会いの可能性
- 位牌
- 遺影
- 墓
- 霊場
- イエの先祖
第3週:日本人の死生観
- 『熊野観心十界曼荼羅』からみた死生観
- 死後霊魂の所在
- 山中他界観
- 山上霊地への歯骨納骨
- 供物からみた死後の死者
- 死者への想い
- 死者からカミへ-柳田國男の所論-
- 伝統社会の死生観
第4週:社会変動の中の死の文化
- 死の理解の変化-アリエスの所論-
- わが国における死の理解
- 『中央公論』にみる死の扱いの変化
- 墓碑銘からみた死生観の変化
- イエの崩壊
- 葬送習俗にみる近年の動向
- イエ亡き時代の死者のゆくえ
- memento mori
課題内容
理解度確認クイズ(多肢選択):各2点×32=64点
最終レポート:36点