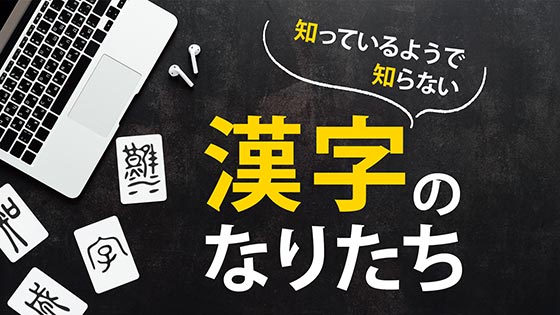立命館大学では、アカデミックな講義をライブ配信で受講できる「立命館オンラインセミナー」を開講しています。詳細は以下よりご覧ください。
※立命館アカデミックセンターホームページに遷移します。
講座内容
この漢字って、「なんでこんな形?」「どうしてこう読むの?」。
わたしたちにとって⾝近で、当たり前のように使っている“漢字”は、他の⾔語や⽂字とは⽐べものにならないほどの情報、魅⼒、メッセージが込められています。
しかし、漢字の⼀⽂字⼀⽂字がどのようにできたのか、なぜこの読み⽅になったのか、こうした「なぜ?」を考えることはあったでしょうか。
本講座は、漢字を暗記・記憶することではなく、その⽂字の「なりたち」や「つながり」を考え、想像しながら、⼤⼈も⼦どもも楽しく漢字を学ぶことを⽬的としています。
・「『⼈』という字は、どうしてこの形?」
・「『⻭』という漢字には、なぜ『⽌』がつくの?」
・「『敗北』という⾔葉になぜ『北』?」
・「漢字には、どうして『読み⽅』がたくさんあるの?」
こうした「なぜ?」の先には、これまで⽬を向けることの少なかったあらたな漢字の世界が広がっています。
その背景にある⾃然・社会・⽂化を知ると、漢字を学ぶことがもっと楽しくなります。
漢字の世界を知ることで培った「なぜと考える⼒」「原理を押さえて繋がりを⾒つける⼒」「基礎から推測する⼒」は、他の分野にも広がっていきます。
⼤⼈も⼦どもも⼀緒になって、漢字の世界を楽しみましょう。
※講義動画収録時期:2021年
立命館大学が提供する現在開講中の講座一覧はこちら!
詳細はこちら:https://gacco.org/ritsumei_ACR/
第1章 漢字のはじまり
- 第1回 ⽂字と記号のちがい
- 第2回 漢字はこうして⽣まれた その1
- 第3回 漢字はこうして⽣まれた その2
第2章 漢字のできかた・つくりかた
- 第4回 モノのかたちからできた漢字
- 第5回 組み合わせからできた漢字
第3章 漢字のなりたち・つながり
- 第6回 「部⾸」ってなに?
- 第7回 「⼈」からつながる漢字
- 第8回 「⼿」からつながる漢字
第4章 読み⽅のひみつ
- 第9回 「⾳読み」中国からやってきた?
- 第10回 「訓読み」⽇本のことば?
講師・スタッフ紹介
久保 裕之(くぼ ひろゆき)
<略歴>
1987年3⽉ ⽴命館⼤学法学部 卒業
2005年7⽉ 学校法⼈⽴命館 ⼊職 ⽩川静記念東洋⽂字⽂化研究所 ⽂化事業担当(現在に⾄る)
2015年3⽉ 放送⼤学⼤学院 ⽂化科学研究科 ⽂化科学専攻修⼠課程 修了
<立命館大学 ⽩川静記念東洋⽂字⽂化研究所について>
立命館大学 ⽩川静記念東洋⽂字⽂化研究所は、東洋の文字文化について高度な研究業績を持つ文化勲章受賞者 故・白川静立命館大学名誉教授の研究成果をもとに、東洋文字文化について広く社会一般を対象とした教育と普及をおこない、また学術研究の分野において東洋文字文化研究の振興と高度化を図ることを目的に設立されました。