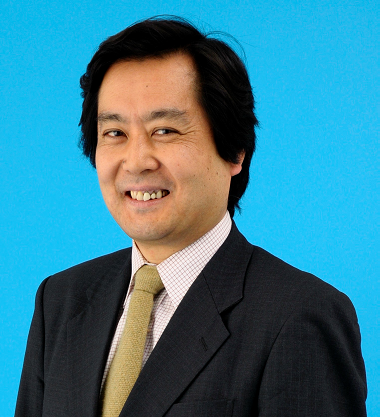講座内容
2015年は、世界が持続可能な未来に向けて進むべき方向を決める重要な年となりました。この年に採択された二つの国際的な合意が、私たちの社会や企業に大きな影響を与えています。それが「SDGs(持続可能な開発目標)」と「パリ協定」です。
SDGsは、国連持続可能な開発サミットで採択され、貧困や気候変動、生物多様性、エネルギー問題など、世界が解決すべき課題を示した目標です。これらの課題を克服し、持続可能な社会を築くために、企業の役割はますます重要になっています。
パリ協定は、COP21(第21回国連気候変動枠組条約締約国会議)で合意され、地球温暖化を防ぐための目標を設定しました。この協定では、「産業革命前と比べた気温上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求すること」が掲げられました。しかし、2℃目標では1.5℃目標と比べて気候変動による被害が増大することが指摘されたため、COP26で採択された「グラスゴー気候協定」では、「産業革命前からの気温上昇を1.5℃までに抑える」ことが事実上の共通目標となりました。1.5℃目標を達成するには、エネルギー消費の多いビジネスモデルを見直し、今世紀の早い段階で温室効果ガスの排出を実質ゼロにする必要があります。
これらの国際的な枠組みにより、世界は持続可能な社会への転換を加速させており、ビジネスの脱炭素化は避けられない課題となっています。これまで日本企業はエネルギー消費の多い経営モデルを強みとしてきましたが、今後は「環境(E)」「社会(S)」「ガバナンス(G)」の観点から、事業のあり方を再構築することが求められています。
SDGsやパリ協定をリスクと捉える経営者もいますが、これらは単なる制約条件ではなく、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性も秘めています。そもそも、ビジネスとは社会課題を解決することが本来の使命です。企業はSDGsが示す課題の中から新たなビジネスチャンスを見出し、それを成長戦略に組み込むことが求められています。
多くのビジネスは社会課題の解決から生まれています。例えば、法律やルールが未整備な分野や、既存の仕組みが機能していない分野には潜在的な市場があります。取り残された課題の解決策を提供することで、新たなビジネスが生まれます。社会課題の解決に挑み、新しい社会の姿を提供する企業に対して、ステークホルダーの多くが共感するでしょう。
現在、日本企業はグローバル市場での存在感が薄れつつあります。そのため、サステナビリティを軸とした新しいビジネスの創出が強く求められています。気候変動などの環境変化に適応するには、従来のビジネスモデルに固執せず、柔軟な発想を持つことが重要です。
企業は、既存のビジネスの意義を問い直し、広い視野で事業戦略を見直す必要があります。今こそ、「アウトサイドイン・アプローチ」(外部の視点から自社の戦略を考える手法)を取り入れ、持続可能な未来に向けたビジネスモデルを構築する時期に来ています。サステナビリティとは、サバイバビリティ(生存可能性)とも言い換えられます。環境や社会の変化に対応しながら、企業は常に変革を続け、社会が求める価値を創出しなければなりません。
この講座を通じて、世界的なサステナビリティの潮流を正しく理解し、カーボンニュートラルを目指した事業変革、多様性を尊重し生きがいを生み出す働き方改革、経営の透明性を確保するコーポレートガバナンスの実践など、日本企業が直面する課題への認識を深めることを期待しています。
各回のテーマ
第1週:企業の存在意義を問い直す
- 第1回 SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは
- 第2回 求められるパーパス経営
- 第3回 企業評価の新しい尺度
- 第4回 ケーススタディ 日本版パーパス経営の源流
第2週:カーボンニュートラルへの取り組み
- 第1回 GX(グリーントランスフォーメーション)とは
- 第2回 GXを後押しするESG投資
- 第3回 GXを支えるイノベーション
- 第4回 期待されるブルーカーボン
第3週:人的資本経営とは何か
- 第1回 なぜ、人的資本経営が求められるのか
- 第2回 DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)とは
- 第3回 企業価値を高める人材育成とは
- 第4回 ケーススタディ 日本版人的資本経営の源流
第4週:攻めのコーポレートガバナンス
- 第1回 コーポレートガバナンス・コードとは
- 第2回 経営の透明性をどう高めるか
- 第3回 社外取締役の意義
- 第4回 ステークホルダーとの対話