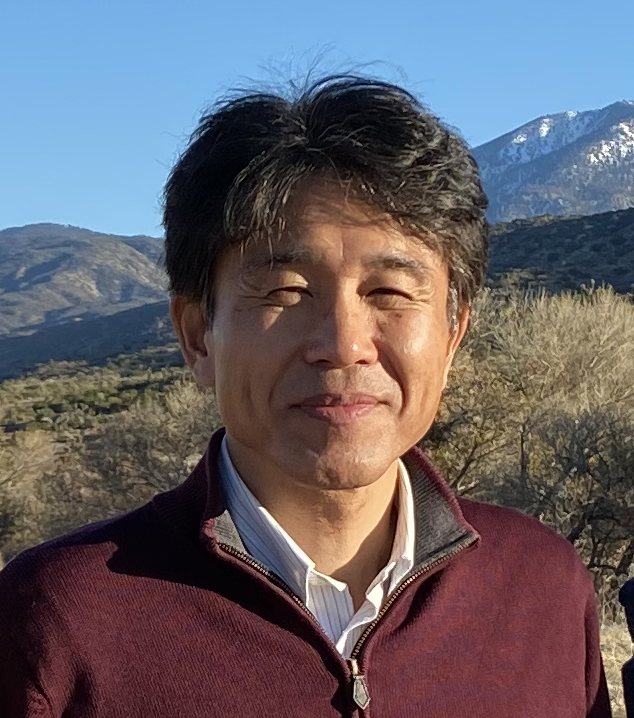
遠田 晋次(とおだ しんじ)
東北大学災害科学国際研究所教授(災害評価・低減部門)(博士(理学))
1966年12月生まれ。宮崎県出身。
鹿児島大学理学部卒業後、 東北大学大学院理学研究科前期博士課程修了、電力中央研究所研究員、同所属中に米国地質調査所(USGS)客員研究員、東京大学地震研究所助手、産業技術総合研究所活断層研究センター研究員、京都大学防災研究所准教授を経て、2012年10月から現職。現在、日本活断層学会副会長、地震予知連絡会会長。専門は地震地質学・活断層研究で、内陸大地震の長期予測のほか、地震の連鎖性に関する研究にも取り組んでいる。
主な著書

